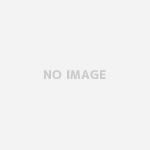今日は簡単なUser認証のプロトタイプといえば恰好はよいが、
- パスワードの入力
- パスワードの突き合せ
- パスワードつきあわせの結果によりメッセージを変える
name = 'Mary'
password = input()
# password = 'Pass'
if name == 'Mary':
if password == 'Pass':
print ('access granted')
else:
print ('access denied')
しょぼいプログラムではあるが、パスワード認証のロジックはこれすべてこれである。nameをコードに直接書き込んでいる。これをICカードで名前を読み取るようにする。input()をいまコンソールからキーボード入力としているが、ここを網膜認証のセンサーと組み合わせて、passwordに網膜画像データを取り入れる。パスワードのつきあわせをデータベースに登録したデータと照らし合わせる。この時に画像データだからある程度の揺れを考慮してあげる。最後のprintのところではドアのセキュリティと連動させれば、これで網膜認証によるアクセスコントロールの出来上がり。
次はループ。面倒くさいのでサンプルのみ
こちらはデバッグなどに使えるループに入っていることを確認するためにループに入るたびにコンソールに文字列を出力
spam = 0
while spam < 5:
print ('Hello')
spam = spam + 1
次に名前入力を求める。ユーザーが何も入力しない場合には無限回廊から抜け出せない。
name = ''
while name == '':
print ('Please type your name')
name = input()
print ('Hello ' + name)
下記はwhile Trueを利用したバージョン。どの言語でもいえるがどちらのステートメントが良いかは実際問題としてコンパイル後のコードがどのようになっているかによる。自分の経験だとbreakを使って明示的にループから抜け出すほうが実行コードに無駄がない気がする。
name = ''
while True:
print ('Please type your name')
name = input()
if name != '':
break
print ('Hello ' + name)
次はforバージョン、ついでに数字の文字列変換とランダム値の生成。数字でコントロールする場合、あるいは文字列トークンを使う場合にはforがwhileより使いやすいが、python1ではどうだろうか。
import random
for num in range(5):
print ('count' + str(num))
print ('randome' + str(random.randint(1, 10)))
数字の変換はお約束でstr(), ちなみに逆はint()。int()は失敗するとfalseを戻すので数字形式のチェックにも使える。こんな感じか if int(target) :。
ランダム値の生成はrandom.randintで簡単に取得できる。その前にライブラリをimportで読み込むこと。
いよいよ関数呼び出し。まずは簡単なところで。テキストをパラメータで送ってコンソールに出力。関数の定義はdefで行う。
def Hello(name):
print(name)
Hello('AAA')
Hello('BBB')
Hello('CCC')
パラメータを送ったら今度は戻り値を取得してみる。戻り値はreturnによりメインロジックに戻せるわけだが、変数の型はあまり気にしていないようだ。コンパイル時エラーが期待できないとなると、処理に自分で組み込む必要がある。これは少々めんどうくさい。
import random
def translate(p_value):
if p_value == 1:
return ('this is one')
elif p_value == 2:
return ('this is two')
else:
return ('this is three')
print translate(random.randint(1,3))
さてここまでは主にフローコントロール。プログラミングの処理を分岐、繰り返す構文について勉強した。次に出てくるのがList。これが業務アプリケーションではあまり使わないがRの経験を思い出すとやたらListを使っていた記憶がある。Listについては基本操作~応用まで大体利用パターンが決まっているのでとりあえずまとめて実行
#基本操作
spam_x = ['cat', 'dog', 'moose']
print(spam_x[0])
print(spam_x[0:2])
print(len(spam_x))
# 代入
spam_x[0] = 'blackcat'
print(spam_x[0])
# 結合
spam_y = ['elephant', 'penguin']
print(spam_x + spam_y)
# 削除
del spam_x[2]
print spam_x
# 繰り返し
spam_z = spam_x + spam_y
for i in range(len(spam_z)):
print 'Index ' + str(i) + ' in spam_z is: ' + spam_z[i]
# つきあわせ
print ('please enter animal name')
animal = input()
if animal not in spam_z:
print 'we do not have.'
else:
print 'Yes we have'
リストの第二弾
# index search
spam = ['hello', 'hi', 'howdy', 'heyas']
print (spam.index('hi'))
# add item into list
spam = ['cat', 'dog', 'bat']
spam.append('elephant')
print(spam)
# add list item in specified location
spam.insert(2, 'penguin')
print(spam)
# remove item from list
print(spam)
spam.remove('dog')
print(spam)
# sort
spam.sort()
print(spam)
spam.sort(reverse=True)
print(spam)
Listと似た型にtupleがある。表記上、[] と ()を使う違いがあるが、使う上で決定的に違うことがひとつある。Listは変更可能であり、tupleは変更不可能。たとえばListにはトランザクションデータを記録し、tupleにはマスターデータを登録する。
さらにDictionaryを取り扱う。listとtupleはindexは数字のみであったが、dictioaryはindexは数字ではない。またdictionaryでは順番は関係がなくなり、keyとvalueの組み合わせで一つのitemが構成される。
# list comparison #
spam = ['cats', 'dogs', 'moose']
bacon = ['dogs', 'moose', 'cats']
print (spam == bacon)
# dictionary comparison #
eggs = {'cat' : 'this is cat', 'dog' : 'this is dog', 'moose' : 'this is moose'}
ham = {'dog': 'this is dog', 'moose' : 'this is moose', 'cat' : 'this is cat'}
print (eggs == ham)
# get all of keys
for k in eggs.keys():
print('key:' + k)
# get all of value
for k in eggs.values():
print('value:' + k)
# check existence of key and value.
print('cat' in eggs.keys())
print('penguin' in eggs.keys())
print('this is dog' in eggs.values())
print('this is elephant' in eggs.values())
# retrieve data with key.
print('cat:' + eggs.get('cat'))